有価証券の相続についての疑問を解決!

※こちらの情報は2024年3月時点のものです
本年1月から新しいNISA(少額投資非課税制度)が始まったことは御存じでしょうか?この新NISAをきっかけに、株式、投資信託等の有価証券を保有する個人投資家が増えていくことが見込まれています。そんな中、今回は有価証券の相続についてよくある3つの疑問をQ&A形式でご説明したいと思います。
Q1.
亡くなった父は株取引をやっており、証券口座も複数保有していたはずです。相続手続にあたり、どのように確認したらよいでしょうか。
A.
お父様が残されたメモなどで保有口座の把握ができない場合、いくつかの方法で確認する事ができます。
“取引残高報告書”という書類が証券会社より届いている可能性があります。また、株を保有していると、“配当金のお知らせ”といった郵便物が届いている場合もあり、それらから保有している株式や取引していた証券会社を確認することができます。その他にも、配当金や分配金が銀行口座に振り込まれていることがあり、保有している有価証券が何なのか分かることもあります。
オンライン取引をしていたようだが、取引口座のIDやパスワード類が見つけられずオンラインで調べられないという場合は、必要書類を次の方法で証券保管振替機構に送ることにより確認できる可能性があります。
手続きの方法
必要書類を証券保管振替機構に送ります。
- 登録済加入者情報開示請求書等(同機構のホームページよりダウンロード可能)
- 本人と相続人の確認書類(除籍、戸籍謄本等)
- (旧住所で調べる必要がある場合)本人の旧住所の確認書類(住民票や戸籍の附票又は旧住所が記載された株主宛ての配当金計算書等)
※手続きは有料のため、調べる株式が非常に少額の場合は、手続費用がその価額を上回る可能性もあります。
Q2.
相続した株式や投資信託等の有価証券は、どのように課税価額を評価するのでしょうか。
A.
その有価証券の種類によって評価方法が異なります。
上場株式
原則として、次の(1)から(4)までの価額のうち、最も低い価額が評価額となります。
- 相続の開始があった日の最終価格
- 相続の開始があった月の毎日の最終価格の月平均額
- 相続の開始があった月の前月の毎日の最終価格の月平均額
- 相続の開始があった月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
取引相場のない株式(出資証券)
取引相場のない株式(非上場株式等)は、相続や遺贈などで株式を取得した者が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主かの区分によって、それぞれ原則的評価方式か配当還元方式により評価しますが、評価は必ずしも容易ではありませんので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
公社債
公社債の評価もかなり複雑ですが、例えばそのうち利付公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で公表されている課税時期の最終価格に源泉税相当額控除後の経過利息を加算して評価します。
投資信託
上場証券投資信託は、上場株式の評価方法を準用して評価し、非上場証券投資信託の場合は、相続開始日において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。
Q3.
亡くなった父の証券口座に株や投資信託があります。相続の際は全て現金化することによってしか分割出来ないのでしょうか。
A.
相続人がお父様と同じ証券会社に口座を開設すれば、現金化せず株数や口数で分割したり、そのまま移管したりすることができます。現金化したければ、移管後に売却することもできます。

■サービスのご紹介
企業の総合病院🄬シーエーシーグループ/TSCでは、経営者様のあらゆるニーズに各分野の専門家がワンストップサービスでお応えします。
人事・労務・経理等のアウトソーシングを是非ご利用ください。
■企業の総合病院🄬シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/

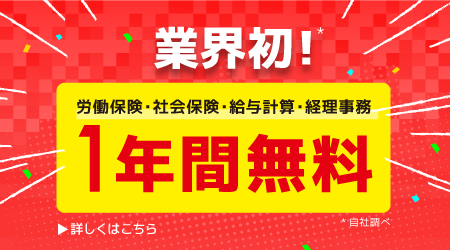
.png)

